The Science of the Swastika [Intellectual History]
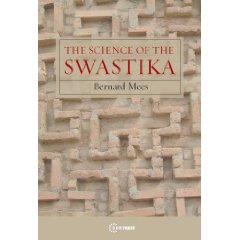
Bernerd Mees
The Science of the Swastika
Praha: CEU Press 2008, viii+363 p.
Preface
Introduction:"Issues concerning the Teutons"
Ch.1: The tradition of Völkisch Germanism
Ch.2: History and intuition
Ch.3: Origins of ideographic studies
Ch.4: Germanic Resurgence
Ch.5: National Socialism and antiquity
Ch.6: Intellectual prehistory
Ch.7: Academic responses
Ch.8: The expansion of the Ahnenerbe
Ch.9: Into the academy
Ch.10: Epilogue, aftermath
Conclusion: The secret garden
Abbreviations
Picture credits
Bibliography
Index
* * * * * * * * * *
ナチズムのドイツではある特定の学問に限ってアーネンエルベとよばれる学術団体が保護していた、というのはよく知られている。その一つが古ゲルマン学であり、その重要な構成要素がルーンであった。もちろん学問といっても御用疑似学問である。
ドイツ語ではクラウス・フォン・ゼーをはじめとして、類書がいくつかある。著者名は忘れたが『第三帝国のルーン学』という本もあるし、HZの別冊でアーネンエルベを一冊丸ごと扱ったものもある。ミーズの本書は、おそらく英語で読める数少ない第三帝国の故ゲルマン学研究書である。もちろん大枠についてはかのジョージ・モッセの『フェルキッシュ革命』を邦語で読むことができるが、あくまで概略である。初期ルーンの専門家でもある著者による『スワスティカの科学』は、「Sinnbildforschung」に限定して一書をなしているため、議論は深い(ような気がする)。
研究者は自分の研究対象を次第にさかのぼらせるという悪い癖がある。なぜ悪いのかといえば、たとえば10世紀の研究者が8世紀のことに手をつけた場合、往々にして10世紀におこった事象の起源や関連性という点で8世紀の事象を見ようとするからである。8世紀の事象はコンテクストが違うし、そもそも10世紀に何らかの事象があることを見越して準備されたわけではない。クリス・ウィッカムが、「教会はグレゴリウス改革に収れんする動きを初期中世に見せていたわけではない」と戒めていたが、それはすべての時代に当てはまる。
近年の悪い癖は、歴史記述の大枠細部を研究者の政治的態度に還元する傾向があることである。E・H・カーの「歴史を知りたければ歴史家を知れ」の実践であり、それはそれで必要なことであろうが、しかしながら、ナチとの関係をほじったところでフランツ・デルガーやパーシー・シュラムの学問の意味や価値はわからない。本書が論じるようにルーン研究も後ろ暗いものがつきまとわないでもないが、だからといってルーン研究が悪いというわけではないし、ヴォルフガング・クラウゼやヘルムート・アルンツらの研究はいまでも参照に値する。ヘルベルト・ヤンクーン抜きでハイタブ研究はできない。「褐色の学問」の評価は「帝国の学問」の評価と並行する。
プラハの大学出版局で刊行されたが、ここの本はなぜか日本のアマゾンで手に入る。中世関係は結構いい本が安価であったりする。

