大聖堂ものがたり [Arts & Industry]
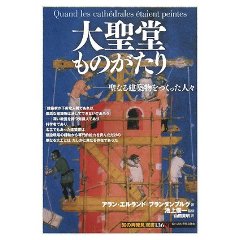
アラン・エルランド=ブランダンブルグ(池上俊一監訳/山田美明訳)
大聖堂ものがたり 聖なる建築物をつくった人々(知の再発見叢書136)
創元社 2009年 186頁
第1章 新たな世界
第2章 建築家
第3章 表現手段
第4章 建設現場
資料編
Index
図版索引
参考文献
Alain Erlande-Brandenburg
Quand les cathédrales étaient peintes.
Paris: Gallimard 1993
* * * * * * * * * *
この「知の再発見叢書」は、図版が多い一般向けの導入書とはいえ、バカにできない。執筆者はフランスの超一流どころがつとめているからである。ドイツや日本でこんなシリーズを立ち上げると「学者がなにをやっとんじゃ」と叱責されるのがオチだが、百科全書の伝統が脈打つフランスではむしろ賞賛される。小遣い稼ぎとか手遊びというわけではなくて、一般読者との対話を重視する。かの地で哲学カフェが流行るのもむべなるかな。
著者は古文書学校を出て、現在高等実践研究所の教授。『大聖堂』という、大聖堂の社会史で著名。教会建築の研究と言えば、通常は工学部を出た建築史家の手になる。ヴォルフガング・ブラウンフェルスとかオットー・フォン・ジムソンとかロバート・マークとかの翻訳がそうであるし、中世建築史を支えてきた飯田喜四郎もそうである。もちろんこれらの本は大変勉強になるのだが、人文系の人間には建築工学は厳しすぎる。ゴシック建築は確かにフライングバットレスによる重量の拡散(だったかな)という建築工法の革新があったからこそ可能になったわけだが、その数式を出されてもねえ。とはいえ工法も文書もどちらも大切なんだと思います。
著者が用いる史料は多岐にわたる。図像のような建築表象であったり、設計図の青写真であったり。一般史のわたくしにとっては珍しい史料ばかりなので、ああこんなものまで残っているのかと目をと落とすだけで楽しい。著者によれば、中世の建築社会史に関しては、利用されていない中世後期の文書がまだ大量にあるとのこと。専門用語が目白押しなので、解読が難しいらしい。実際に大工の経験を積んだ古文書学者でもいれば、話はどんどん進むだろうと思うのだが。
教会建築は中世学にとって宝庫である。大聖堂などそもそも中世社会の代名詞のようなものである上に、建築史、美術史、教会史、政治史、文化史などどの分野の研究者にとってもアプローチ可能な対象である。もうなくなった方だが、九州大学に森洋という先生がいた。テオフィロスとかシュジェールの翻訳とかをされているので、美術史家にも知られている西洋中世史家である。彼は次のような論文を書いている。
森洋「初期ゴシック教会堂の成立とその社会的思想的背景 12世紀に於ける教会堂のロマネスクよりゴシックへの様式転換に関する一考察」『史学雑誌』62編2号(1952年)121-167頁
学部の頃に読んで面白いことをしている人がいるもんだと思った。パノフスキーの「ゴシック建築とスコラ学」がウォーバークの紀要(だったかな)に掲載されたのが1951年だったと思うので、ほとんど刊行の時期は変わらない。内容は忘れてしまったが、パノフスキーとは違うアプローチをしていたように思う。歴史家からの建築史へのアプローチという、日本では稀有な事例である。

