Emotional communities in the early middle ages [Early Middle Ages]
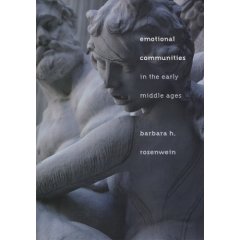
Barbara H. Rosenwein
Emotional Communities in the Early Middle Ages.
Ithaca & London: Cornell UP, 2006, xv+228 p.
List of Tables and Map
Prefatory Note
Acknowledgments
Abbreviations
Introduction
1. The ancient legacy
2. Confronting death
3. Passions and power
4. The poet and the bishop
5. Courtly discipline
6. Reveling in rancor
Conclusion
Selected Bibliography
Index
* * * * * * * * * *
著者はシカゴにあるロヨラ大学教授。クリュニーの専門家として著名であるが、近年は初期中世における感情の研究を集中的に進めている。本書は古代末期からメロヴィング期までを対象としているが、議論の枠組みは専門誌に公表した「感情の共同体」論文を敷衍したもの。
Barbara Rosenwein, Even the Devil(sometimes)has feelings: emotional communities in the early middle ages, in: The Haskins Society Journal 14(2003), p. 1-14.
かつて感情と理性は対置され、前者は後者に従属させられてきた感がある。洋の東西を問わず人前では感情を理性で抑えてこそ一人前とされるが、それはコミュニケーションの場で感情を表出することによって、それまで両者の間で結ばれてきた関係を逆転させることも可能であるということにもつながる。感情は心的反応であり、その心的反応は、言語表現、表情、身振り等によって他者に伝達される。そうであってみれば、感情の研究とは、感情が表れる場の研究であるとともに、その表現作法の研究でもあり、感情を読み取ることのできるあらゆるものがテクストとして等価とされねばならない。もちろん歴史家は文献史料を第一のフィールドとするが、それに留まらず文化人類学の手法をいち早く取り入れ、図像史料を分析の俎上にのせたジャン・クロード・シュミットなど、感情研究の開拓者の一人であるとも言える。
ジャン=クロード・シュミット(松村剛訳)『中世の身ぶり』(みすず書房 1996 原著1990), iv+455頁
感情は時代や地域によって異なり、また同一地域においてもその人物が所属する集団によって異なる。そうした「感情共同体」がいくつも重なり合う場が初期中世であり、資料から表現を拾ってインデックス化すれば応用可能な基礎データが得られるだろう。初期中世ならずとも中世社会は、感情のゆれ幅が大きい、もしくは大きく見える人物を集中的に記録する社会であるように思うので、特に12世紀以降の宗教史料は感情研究にとってよい素材であるように思う。また北欧でも具体的な描写に富むサガ資料群に適用すれば、かなり面白いだろう。誰かやらないかな。
しかし感情はただ構成主義的(私は構成主義と構築主義の差を理解していない)にできてゆくものなのだろうか。もちろん人間はそれを取り巻く社会のコードを受け入れることによって成長し「社会的人間」となっていくわけで、そう考えると構成主義の有用性を認めることに吝かではない。しかし経験上、私は人間の幼児が「tabula rasa」であるという見解に同意はできない。ともあれ、人間を扱う歴史家は双方の視点から資料を読み解くべきで、構成主義と個性論いずれもよく考えていかねばならない。そのバランスの取り方に、人文学者であり社会科学者であり、そして資料にその叙述対象が規定される歴史家の特徴があるようにも思う。まだ読んでいないが、
赤川学『構築主義を再構築する』(勁草書房 2006)
には何か参考になるものがあるかもしれない。
歴史学の外では感情の研究は盛んなようで、書店には「感情」や「情動」をタイトルに含んだものがいくつも並んでいる。認知心理学の立場から近年の研究動向を追った論集として、
北村英哉・木村晴編『感情研究の新展開』(ナカニシヤ出版 2006), 290頁
がある。執筆者は講師から院生レヴェルの若手が多い。私は専門化ではないのでまず何を読むべきか自分で判断はできないが、日本人による著作として、
戸田正直『感情 人を動かしている適応プログラム』(認知科学選書24)(東京大学出版会 1992)
遠藤利彦『喜怒哀楽の起源 情動の進化論・文化論』(岩波書店 1996)
が挙げられている。
中世史においても個別の感情研究はいくつかある。一冊の本になっているものを挙げると、たとえば「怒り」に関して、
Barbara Rosenwein(ed.), Anger's Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages . Ithaca: Cornell UP, 1998, 256 p.
政治的な場での「怒り」の発露を分析するゲルト・アルトホフの議論が興味深い。アルトホフはドイツ学術協会の特定領域研究によって、中世におけるコミュニケーションの研究を進めているが、当然感情の発露と抑制もその範疇に入る。彼がフィールドとしたオットー朝には、コルヴァイのヴィドゥキントによる『ザクセン人の事績』という大変興味深い叙述史料がある。アルトホフはこれを儀礼という観点から長年扱ってきたが、そこで確認される王侯貴顕の怒りや悲しみの所作は、そのまま感情研究へと転用できる。
Gerd Althoff, Empörung, Tränen, Zerknischung.'Emotionen' in der öffentlichen Komunikation des Mittelalters, in: Frühmittelalterliche Studien 30(1996), S. 69-79.
「悦楽」に関して、
ジャン・ヴェルドン(池上俊一監訳)『図説 快楽の中世史』(原書房 1998), 282頁
「恐怖」に関して、
ジャン・ドリュモー(永見文雄・西澤文昭訳)『恐怖心の歴史』(新評論 1997), 862頁
ジャン・ドリュモー(佐野泰雄他訳)『罪と恐れ 西欧における罪責意識の歴史 13世紀から18世紀』(新評論 2004), 1196頁
特に宗教は、人間の未来を支配し恐怖を左右することで成立するという面があるため、感情研究にはうってつけの素材を与える。ジャン・ドリュモーはコレージュ・ド・フランスの教授で、もともとは16世紀ローマ経済史で博士号を取得したが、その後宗教心性の研究に傾斜した。多作の上に一冊一冊が分厚く、フランス語原著での読破など専門でもないので考えもしなかったが、ありがたいことにかなりの著作が邦訳されている。採算があうかどうかもわからないこのような企画を敢行した出版社と膨大な時間をかけて翻訳した訳者には感謝したい。
というような内容を書いていたのだが、保存ボタンをおすと一瞬で消えた。ふざけた話ではあるが、データは自己防衛しなければならないということを久しぶりに痛感した。

