The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [Literature & Philology]
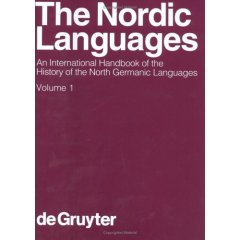
Oskar Bandle(ed.)
The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22). 2 vols.
Berlin & New York: Walter de Gruyter, 2002-05, xxxiv+2208 p.
Volume 1
Preface
Abbreviations
I. Introduction
II. Perspectives in research history I: From the beginnings to the middle of the 20th century
III. Perspectives in research history II: The contribution of Nordic research to historical linguistics(until 1950)
IV. Perspectives in research history III: Theoretical and methodological perspectives in current historical linguistic description(after 1950)
V. Perspectives in research history IV: The contribution of Nordic dialectology
VI. Nordic language history as a part of social and cultural history
VII. Nordic as a part of Old Germanic
VIII. Ancient Nordic(1th-7th century)
IX. From Ancient Nordic to Old Nordic(from the 6th century until 1100)
X. Old Nordic(from 1100 to the mid-14th century) I: General survey, tradition
XI. Old Nordic II: Grammatical system, lexicon, texts
XII. Old Nordic III: The ecology of language
Volume 2
XIII. From Old Nordic to Early Modern Nordic(from the mid-14th to the mid-16th century)
XIV. The development of the Nordic languages from the mid-16th century to the end of the 18th century
XV. The Nordic languages in the 19th century
XVI. The Nordic languages in the 20th century
XVII. Special aspects of Nordic language history I: Typology
XVIII. Special aspects of Nordic language history II: Social stratification
XIX. Special aspects of Nordic language history III: Special languages and languages for specific purposes
XX. Special aspects of Nordic language history IV: Languages cultivation and language planning
XXI. Special aspects of Nordic language history V: Language contact
Index of names
Index of subjects
* * * * * * * * * *
歴史家はテクストを対象とする。今でこそ、テクストは文字に限定されないが、それでも文字テクストが最も情報を与えてくれる、と多くの歴史家は信じている。したがって、歴史家は表象記号としての文字とその意味内容を規定する言語とは切っても切れない関係にある。19世紀以来の言語学が提供する学知は歴史家にとって不可欠である。
北欧は言語学が盛んである。これもどこかに書いたように思うが、とりわけデンマークはラスムス・ラスク以来、著名な言語学者を多数輩出してきた。移民が増加してなお高々人口600万弱の国に、これほどかと思うくらいである。コペンハーゲン大学は最近大幅な改組があったため、今はどうなっているのかわからないが、私が滞在していた頃、「北欧言語学科 Nordisk filologi」は人文学部で最大の規模を誇り(歴史学がおそらく二番目)、それに比例して教員の数も付属図書館の規模も圧倒的であった。それにも増してこの学科のプライドの源は、デンマークが世界に誇る「アルニ・マグヌッソン研究所」が併設されていた点にあった。
アルニ・マグヌッソン(1663-1730)はコペンハーゲン大学で教鞭をとる傍ら、アイスランド(当時デンマーク領であった)を含む北欧中から写本の収集にいそしんだ。彼の死後、大学に寄贈されたコレクションをもとにその名前を冠した研究所が設立され、コペンハーゲンは、その写本の豊かさゆえ、ウップサーラと並ぶ古ノルド語研究のメッカとなった。戦後の1965年、研究所と王立図書館にあるアイスランド起源の写本は、1944年に独立したアイスランドに返還しようとの議会決定がなされ、1971年から97年にかけて、アイスランド大学内に新設された「アルニ・マグヌッソン研究所」に順次送り返された。その中で最も著名な写本は、エッダの記される「王の書」と、美麗な挿絵のある「フラート島本」であり、後者は研究所の陳列室に行けば誰でも目にすることができる。なおこの研究所は、2006年に、アイスランド語研究所、辞書学研究所、シグルズル・ノルダル研究所、アイスランド地名研究所という他のアイスランド語関係の研究所とともに、一つに糾合された。
本書は、その頁数からもわかるように、北欧言語のハンドブックとしては決定版となる。そもそもこの「Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft」というシリーズが、言語学の各分野にとって、まず手にするべきハンドブックを提供しており、「言語科学の歴史 Geschichte der Sprachwissenschaft」、「固有名詞学 Namenforschung」、「文字とその使用法 Schrift und Schriftlichkeit」、「言語史 Sprachgeschichte」といった、歴史家にも興味深い巻が既に用意されている。言語学科を要する大学であれば、おそらくどこでも持っているのであろうが、これらが並んでいる棚は壮観である。なお、一冊あたり10万円位するので、科研費でもない限り個人で買うことはまあ無理でしょう。
古い時代のことばに相当の頁が割かれているので、中世以前に関心を持つ向きにはどこを拾っても役に立つ。しかし歴史学者にとって不可欠となるのは、第6章「社会史ならびに文化史としての北欧言語史」であり、ステファン・ブリンクも寄稿している。ルーンに関心があれば、第7章から第9章までが対応する。トーマス・ビルクマン、マーティン・サイアット、リナ・ペターソン、モーテン・アクスボー、ステファニー・ビュルトといった、ルーン学やアイスランド学にはおなじみの名も見える。
北欧言語のハンドブックは、現地語、英語、ドイツ語で、それこそ無数にあり、私などどれがよいのやら皆目見当もつかない。現地語で書かれた言語史は当面読む必要もなかろうと、倉庫にしまってしまった。何もないのも問題なので、とりあえずペーパーバックのある、
Ekkehard König & Johan van der Auwera(eds.), The Germanic Languages(Routledge Language Family Descriptions). London & New York: Routledge, 1994, xv+631
を手元においていた。ゲルマン語なので、北欧に限ったわけではないのだが。日本語で読めるものとしては、二冊良書がある。
アラン・カーカー編(山下泰文他訳)『北欧のことば』(東海大学出版会 2001), 278頁
エリアス・ヴェセーン(菅原邦城訳)『新版 北欧の言語』(東海大学出版会 1988), 212頁
カーカーも故ヴェセーンも、北欧を代表する言語史・言語学者。特に、ルーンや中世スウェーデン語の刊本や翻訳の公刊に尽力したヴェセーンの存在なくしては、現在の中世北欧研究は成り立たなかっただろう。世界的に、グリム以来言語学の中枢に位置した歴史言語学は、構造主義的言語学の台頭に伴って、徐々にその特権的地位を失いつつあると聞くが、歴史学との共同作業という点では、まだまだやるべきことはある。言語学者はそのあたりを、どのように考えているのだろう。
エーコの『完全言語の探求』を読めばわかるように、ヨーロッパにおける言語史は、聖書をスタンダードとした知と、文献や実験による検証に基づいた科学的知がせめぎあう、初期近代が一番面白い。北欧で言えばルーンがまさにその焦点になるのだが、しっかりとした研究はまだ少ない。思想史(idehistoria)としての言語史は、日本でももっと盛んになってくればと思う。

