The Mongols and the West 1221-1410 [Medieval History]
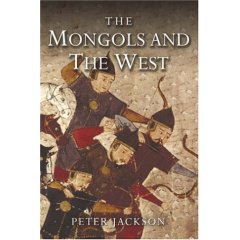
Peter Jackson
The Mongols and the West 1221-1410(The Medieval World).
Harlow: Pearson, 2005, 414 p.
Series editor's preface
Preface
Abbreviations
Note on transliteration
Note on proper names
Note on references
List of maps
Introduction
Ch. 1: Latin Christendom and its neighbours in the early thirteenth century
Ch. 2: A world-empire in the making
Ch. 3: The Mongols invasions of 1241-4
Ch. 4: A remedy against the Tartars
Ch. 5: The halting of the Mongol advance
Ch. 6: Images of the enemy
Ch. 7: An ally against Islam: the Mongols in the Near East
Ch. 8: From confrontation to coexistence: the Golden Horde
Ch. 9: Temür(Tamerlane) and Latin Christendom
Ch. 10: Mission to the infidel
Ch. 11: Traders and adventurers
Ch. 12: A new world discovered ?
Conclusion
Appendix I: The authenticity of Marco Polo's travels
Appendix II: Glossary
Appendix III: Genealogical tables and lists of rulers
Bibliography
Index
* * * * * * * * * *
モンゴルは初期中世ではないのだが、他の項目に分類の仕様もなかったので、とりあえず初期中世としてみた。そのうち変えるかもしれない。
著者は英国キール大学の中世史講座教授。中世ヨーロッパにおける東方世界の接触というテーマになると、必ず見る名前である。しかし論文はよく見るが、単著は初めてかもしれない。英語での類書を見ないので、これは長らく教科書として指定されるものになる予感がする。東洋学というと、フランス、ドイツ、ロシアのイメージが強すぎて、イギリスがどのような状態にあるのか調べたこともなかった。どうなんでしょう。
西洋中世とイスラムの関係を論じたものは、無数にある。日本語にも翻訳されているリチャード・サザーンとかバーナード・ルイスとかの基本書に加えて、なかなか面白かったのが、
L・ハーゲマン(八巻和彦・矢内義顕訳)『キリスト教とイスラーム 対話への歩み』(知泉書館 2003), 199+55頁
出版の契機はおそらく9・11にあり、題名も一般書のように見えるが、実はかなり重厚なヨーロッパ側のイスラーム認識史である。他方、ヨーロッパとモンゴルとの関係について論じた邦語文献は少ない。邦語文献どころか欧語文献も、まとまったものは少ないのではないだろうか。個人的に手元においていたのは、
Felicitas Schmieder, Europa und die Fremden: die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert(Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 16). Sigmaringen: J. Thorbecke, 1994, 396 S.
である。現在はハーゲン大学の教授職にあるが、ながらくヨハンネス・フリートの助手をつとめており、来日経験もある。早稲田での講演は聞いたが、マシュー・パリスによるモンゴルイメージが印象に残っている。
元寇の歴史を背負う日本人でもあるし、モンゴルには以前から興味を持っていた。ヨーロッパ史の講座にもかかわらず、仕事先で一時間をかけて講義したこともある。大量の資料を所蔵し、東洋学の一つの中心でもある日本、とりわけ京都では、当然のことながら最新のモンゴル研究が生産されている。現在のリーディング・スカラーは京都大学の杉山正明であり、あまりのモンゴルびいきにときおり引かないでもないが、文明論風味の叙述は、これぞ歴史の醍醐味と雄大な気持ちにさせる。しかし書き過ぎである。可能な限り目を通しているのだが、読むほうの身にもなって欲しい。とはいえ、本田實信の衣鉢を継ぐ杉山が、単なる概説屋ではないことを証明するのが、
杉山正明『モンゴル帝国と大元ウルス』(京都大学出版会 2004), 548頁
1992年の大河ドラマでは、モンゴル側の時代考証もしており、専門知を最も効果的な手段で社会に還元している。私が歴史家としてこうありたいと思う一人である。
西洋中世史など、文献学言語である英独仏伊羅の五ヶ国語と、自分の関係する国の言葉が読めればとりあえずは何とかなるが、モンゴルは、研究文献を読むための英独仏露中に加えて、系統の異なる言語家族に属する何十もの資料言語を渉猟せねば、その実態が見えてこない、という。どの分野を専攻するにせよ必須となる資料ですら、モンゴル語の『元朝秘史』と、ラシード・ウッディーンによるペルシア語の『集史』という二つの根本史料に加えて、漢文、ペルシア語、ラテン語の資料もある。断片的なものも含めれば、それは膨大となろう。翻訳はおろか、校訂が進んでいないものもある。簡便な資料梗概は、次の本の第8章。
デイヴィド・モーガン(杉山正明・大島淳子訳)『モンゴル帝国の歴史』(角川書店 1993), 290頁
モーガンの概説は、ブラックウェル社の「Peoples of Europe」の一冊で、1986年に初版が出たが、毎年増刷されている基本文献らしい。1945年生まれのモーガンは、現在アメリカのヴィスコンシン大学歴史学部の教授職にあるが、ピーター・ジャクソンとともに、ギョーム・ド・リュブルクの旅行記の翻訳もだしている。英米圏におけるモンゴル研究の第一人者である。本書のあとがきに、欧米の研究者はペルシア語資料を、日本や中国の研究者は漢文資料を中心に論を組み立ててきた、とある。これを杉山は「国際分業」と述べているが、そういう時代でもなくなってきたのだろう。そのようにやるべき下積みが増えた割には、成果を早く出せとうるさい時代でもある。
たかが数ヶ国語でギャーギャー喚いている私には、想像を絶する世界である。東洋学の至宝ポール・ペリオを読んだときも思ったのだが、一日何時間勉強すれば、このような高みにまで達するのだろうか。
なお、西洋史の側からもよい研究書が上梓された。
栗生澤猛夫『タタールのくびき ロシア史におけるモンゴル支配の研究』(東京大学出版会 2007), 472頁
筆者の論文は出るたびに目を通していたが、一冊にまとまり便利になった。頁の過半をアレクサンドル・ネフスキーの研究が占めているが、第三章の研究史整理は出色である。北欧とモンゴルの関係を論じた研究を寡聞にして知らないが、あるのかね。

